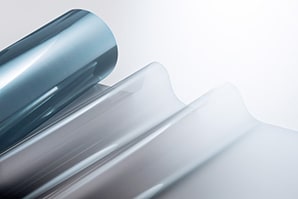SQUID代替を可能にする生体磁気センサのプロトタイプ
常温で微弱な生体磁場の計測のために設計された高感度センシング
世界初、常温センサによる心臓の磁場分布の可視化に成功
TDKは“未来を引き寄せる(Attracting Tomorrow)”技術の一つとして、多種多様なセンサの開発に注力しています。微弱な生体磁場の計測を目的に設計された磁気センサのプロトタイプもその一つ。現行の心電計では発見できないお腹の赤ちゃんの心疾患、早期検出が困難な虚血性心疾患など、こうした問題のソリューションとなる可能性が生まれてきます。
TDKはHDDヘッド製造で培ったスピントロニクス技術によるMR(磁気抵抗効果)素子技術を応用展開して、小型生体磁気センサのプロトタイプを開発。これらのプロトタイプセンサは、現在SQUID(スクイド)磁束計でしか測定できない微弱な生体磁場のセンシングを可能にするために設計されたものです。また、TDKでは東京医科歯科大学大学院との共同研究により、多チャンネルのセンサアレイによる生体磁場測定システムのプロトタイプを開発し、MR磁気センサによる心磁界の概念実証(Proof-of-Concept: PoC)測定と心臓磁場分布の可視化(イメージング)に世界で初めて成功しました。現在開発中のMR磁気センサを用いたプロトタイプシステムは、液体ヘリウムの冷却装置(デュワー)を必要とする高価で大がかりなSQUID磁束計とは異なり、常温(非冷却)でも高感度な測定ができるうえ、コンパクトで操作性・可搬性にもすぐれるため、心磁計などの医療診断用ばかりでなく、ヘルスケアやスポーツ科学などの分野でも活用が期待できます。
TDKのプロトタイプMR生体磁気センサの設計における特長
- スピントロニクス技術によるMR素子を利用した小型生体磁気センサ
- SQUID領域に迫る数十pT(10-11T)の磁気分解能の達成に向けて現在開発中
- 心磁界、筋磁界などの生体磁場を常温(非冷却)・非侵襲での測定に使用できるよう設計
- 多チャンネルのセンサアレイにより心臓の磁場分布の可視化できるよう設計
- 冷却システムが不要
- 可搬性を考慮した設計
- 東京医科歯科大学大学院との共同研究
- 東京医科歯科大学が通常の環境下(磁気シールドルームレス)における心磁計測を世界で初めて成功(2024年)
CONTENTS
背景
心臓病は、がん(悪性新生物)や脳血管疾患(脳卒中)とともに、世界的にも死因疾患の上位を占めています。心臓の活動のようすを調べる検査機器として、心電計(ECG: electro-cardiograph)が広く利用されています。
心臓の電気的活動の発生源は、右心房にある生まれつきのペースメーカーである洞結節という組織です。洞結節から発生した電気信号は、まず心房全体に伝わったあと、房室結節という組織を経由してから、左右に分岐して心室全体に伝わり、心臓のリズミカルな拍動が繰り返されます。これを刺激伝導系といいます。この心臓の電気的興奮の伝達は、体表面の各部の間では電位差として現出します。そこで、四肢や胸部などに取り付けた複数の電極で電位差を検出して増幅し、波形などで表示・記録するのが心電計です。
図1に心臓の刺激伝達系、心臓の活動電流の基本的な流れ、および典型的な心電波形の模式図を示します。P波は心房の収縮、QRS波は心室の収縮にともなう波形、T波、U波は心室の興奮が収まっていく過程の波形です。
図1 心臓の刺激伝導系と心電波形
もし心臓の詳細な電気興奮を観察できれば、飛躍的に診断の精度が上がります。心磁計(MCG: magneto-cardiograph)は、こうした問題に対処するために、目下開発・試験されています。電磁気学の「右ねじの法則」に従い、電流が流れると、周囲には磁界が発生するので、理論上は、心臓周辺に発生した磁界を測定すれば、電流の流れや部位が推定できます。心磁計のもう一つの期待される長所は、体表面に電極を取り付けることなく、着衣のまま完全に非侵襲で測定できるように設計されている点です。ただし、心磁界はきわめて微弱な生体磁場であり、心磁計には高感度な磁気センサが不可欠となります。
磁気センサの種類と生体磁場
初の心電図は1903年、オランダの生理学者W・アイントホーヘンによって考案された装置で測定されました。これに対して心磁界は、地磁気の100万分の1以下という、きわめて微弱なものであるため、初めて測定されたのは20世紀後半の1963年のことです。これは200万回も巻いた1対の磁束検出コイルを用いて測定されました。その後、地磁気などからの擾乱を防ぐために、特別な磁気シールドルーム内で測定が行われるようになりましたが、それでも心臓から磁界が発生しているのを確認できる程度で、心疾患の診断に役立つほどの精度はありませんでした。
生体磁場の測定に大きな前進をもたらしたのは、1970年頃に開発されたSQUID磁束計です。SQUIDは「超電導量子干渉素子:superconducting quantum interference device」の英略語で、超電導体を用いたコイルの一部にジョセフソン接合をもたせた磁気センサです。もともとジョセフソン接合素子はコンピュータの処理速度を高めるための演算素子として開発されたものですが、磁気にきわめて敏感であることから高感度な磁束計として応用されたのです。このSQUID磁束計により、心臓の活動にともなう心磁界ばかりでなく、筋磁界、脳磁界の測定も可能になりました。
しかし、SQUIDを機能させるためには、液体ヘリウムによる超電導コイルの冷却や、磁気的ノイズを遮断するための特殊な磁気シールドルームを設置する必要があり、システムは大がかりで高価なものとなります。
心磁図と対照しながら心電図を解析することで、さまざまな心疾患の診断に有効であることは、多くの論文により指摘されています。しかし、SQUID磁束計にかわるきわめて高感度な磁気センサがあれば、実用的な心磁計の開発と普及がよりすすむ可能性があります。そこで、TDKが現在開発中なのが、先進のMR(磁気抵抗効果)素子による生体磁気センサであり、SQUID領域の磁気分解能の達成が期待されています。現在、数pTを目標に研究を進めており、今後さらに改良を重ねていく予定です。
実用化されている各種磁気センサの感度(およその測定範囲)と生体磁場の強さを図4にまとめました。なお、磁界(磁場)の強さの単位は[Wb/m]、磁束密度の単位は[Wb/m2]で、両者は透磁率によって関係づけられますが、非磁性体である生体組織の透磁率は、空気と同じくほぼ1であり、この図では磁束密度をもって磁界の強さを表しています。1Wb/m2=1T(テスラ)です。1Tはcgs単位系では104G(ガウス)です。
図2 各種磁気センサとおよその測定範囲
HDDヘッド技術とMR素子の開発
TDKのプロトタイプ生体磁気センサに用いられているMR素子について概説します。
物質に外部磁界を加えると、電気抵抗がわずかながら変化することは古くから知られていて、これは磁気抵抗効果(MR効果)と呼ばれます。ホール効果などともに“電流磁気効果”と総称される物理作用の一種で、電荷を運ぶ電子や正孔が磁界中で移動すると、ローレンツ力が作用して、移動方向が曲げられることで説明されています。半導体や強磁性体の磁気抵抗効果を利用したMRセンサは、自動改札機における切符の磁気データ、紙幣の磁気インクのパターンなどを検出する磁気センサなどとして多用されてきました。
この従来型の磁気抵抗効果とは別に、強磁性体の多層膜などにおいて、抵抗変化率が異常に大きい磁気抵抗効果を示すものがあります。1987年にP・グリュンベルクとA・フェールらによって発見された巨大磁気抵抗効果と呼ばれる現象です。電流磁気効果では説明できず、電子のスピンが関係するスピントロニクスの現象です。
巨大磁気抵抗効果はHDDの読み出し素子として利用され、1990年代後半以降、HDDの記録密度は飛躍的に向上しました。TDKは先進のスピントロニクス技術をいちはやく手中とし、GMRヘッド、TMRヘッドなどのHDDヘッドを次々と開発し、HDDの大容量化に貢献してきました(図3)。
図3 TDKの磁気ヘッド開発とHDDの高記録密度化の推移
本記事でご紹介するのは、HDDヘッド製造で培った薄膜技術を応用したスピントロニクス型のMR磁気センサを用いるよう設計されたプロトタイプ生体磁気センサです。また、これまでスピントロニクス型のMR磁気センサでも、その感度は10nT(10-8T)あたりが限界で、MR素子では不可能といわれていたpTオーダーの磁場計測を可能にするには、センサとしてのSN比を大幅に向上する技術が求められます。
TDKでは生体磁場の100万倍もある地磁気などの環境ノイズをはじめ、MR素子や回路そのものが出すノイズを徹底的に排除することで、従来の約1000倍に相当する数十pT(10-11T)という非常に高い磁気分解能を有する生体磁気センサの開発に取り組んでいます。これはSQUID磁束計の領域に迫るもので、心磁界などの生体磁場の測定も可能になるかもしれません。
スピントロニクス型MR磁気センサの原理
スピントロニクス型のMR素子は、非磁性体の薄膜を強磁性体の薄膜がはさんだサンドイッチ構造となっています。片方の強磁性体膜はピンニング(ピン止め)により、磁化の方向が固定されたピン層(固定層)ですが、もう片方の強磁性体膜の磁化の向きは、外部磁界の方向に追随するフリー層となっています。素子の電気抵抗はピン層とフリー層の磁化の向きの相対角に比例して変化するので、電流の大きさから磁場強度を知ることができます。
図4 MR素子の基本構造とセンサ原理
MR磁気センサは、フラックスゲートセンサやMI(磁気インピーダンス)センサと違って、DC電源を供給するだけで信号が得られ、複雑な発振回路を必要としません。
MR素子は温度特性にもすぐれますが、温度変化によってわずかながら抵抗値が変動します。この温度ドリフトを最小にするため、MR磁気センサにおいては、基板に複数の素子を形成し、ブリッジ構成で差動的に温度補償をします。4素子を組み合わせた一般的なホイートストンブリッジ回路を図5に示します。矢印はピン層の磁化の向きです。
図5 温度補償用のブリッジ構成の例(ホイートストンブリッジ)
初の心臓磁場の可視化に向けたプロトタイプ生体磁気センサの開発・試験
ブリッジ構成の複数のMR素子を組み合わせ、さらに低ノイズ回路などを内蔵させたのが、TDKのMR磁気センサユニットです。TDKではこのセンサユニットを格子状に配列したセンサアレイのプロトタイプを開発し、東京医科歯科大学大学院との共同研究により、MR磁気センサによる心磁界のPoC測定と可視化(イメージング)に世界で初めて成功しました(2016年)。
さらに、TDKでは64chまで多チャンネル化することで、より鮮明な画像を得るために、設計の最適化に取り組んでいます。図6に、TDKのプロトタイプMR磁気センサユニットおよび64ch(チャンネル)のセンサアレイを示します。
図6 MR磁気センサユニット(左上)、および64ch MR磁気センサアレイ
TDKの64ch MR磁気センサアレイを用いた心臓磁場分布のPoC測定・可視化例を図7に示します。青色の波形は心電図(ECG)、緑色の波形は心磁図(MCG)、写真は心臓の磁場分布を、胸部のX線写真に重ねてマッピングしたものです。黒い点はセンサチャンネルで、心磁図の波形は黄色のドット(①②)で示したセンサチャンネルより得られた磁場強度の時間波形です。波形のピークが互いに逆向きになっているのは、磁力線の方向の違いによるものです。
写真中の天気図の等圧線に似た白い閉曲線は、心電図のR波に対応した測定時点における心臓周辺の同じ磁場強度を結んだ等磁場線です。赤色および青色の領域は、磁力線の向きの違いを表しています。赤色の領域の磁力線は吹き出し方向を、青色の領域の磁力線は引き込み方向を示しています。心電図のR波は心室の収縮過程にあたり、磁場分布と磁力線の向き、および右ねじの法則より、この時点における心臓の活動電流は緑色の矢印の方向に流れていることが推定できます。
図7 64ch MR磁気センサアレイによる心臓磁場分布のPoC測定・可視化例
TDKが開発した生体磁気測定システムの期待されるメリット
TDKが現在開発中のMR素子を利用したプロトタイプ生体磁気測定システムは、液体ヘリウムの冷却装置(デュワー)を必要とする高価で大がりなSQUID磁束計とくらべて、より低コストで使い勝手がよく、常温(非冷却)で測定できて操作性・可搬性にすぐれるなど、さまざまなメリットが期待されます。
また、磁気シールドルームも比較的簡便なものですむことが期待されます。MRセンサはSQUIDにくらべダイナミックレンジが広いため、簡易な磁気シールド内においても動作することが期待されます。TDKでは、これまでに例のない可搬型小型磁気シールド内で、実際に心臓磁場の分布計測が可能であることを実証しています。加えて、2024年には東京医科歯科大学が通常の環境下(磁気シールドルームレス)における心磁計測を世界で初めて成功しました。
TDKのプロトタイプセンサは非冷却でありデュワーが不要なため、対象部位に合わせてセンサの配置や密度を自由に組み替えられるよう設計されています。
心磁図の臨床的な診断への活用は、まだ開発の初期段階であり、常温で利用できる心磁計の開発が完了し、充分に試験され、関係規制当局に承認されれば、心臓病のみならず、他の疾患の診断にも大革新をもたらすかもしれません。
たとえば、X線写真、X線-CT、MRIなどで得られるのは静的な形態画像です。骨折などの形態的障害の診断には役立ちますが、機能的な診断はできません。このため、心臓疾患の診断に心電計が使われるわけですが、心磁計で計測される磁場は、強度と方向をもつベクトル量です。心臓周辺の磁場分布から発生源を求めること、いわゆる“逆問題を解く”ことにより、将来、活動電流の伝達経路を推定できるようになるかもしれません。また、心電図と対照することで、将来、磁場波形の中から疾患の診断につながる有益情報が得られようになる可能性もあります。
とりわけ、期待されているのは、虚血性心疾患の診断です。虚血性心疾患とは、心筋に送られる血液が一時的に不足する疾患で、重篤化していくと狭心症や心筋梗塞となります。心電図では早期の発見が困難ですが、心磁計による磁場分布の時間的なマッピングにより、将来、検出が可能になるかもしれないからです。
また、心臓に疾患をもって生まれてくる新生児がいますが、胎児の段階で発見できれば、異常時の早期対応や出産後の処置もスムーズに進みます。
子宮内の胎児は、胎脂と呼ばれる物質で覆われています。胎脂は電気絶縁性が高く、心臓からの電流をほとんど遮断してしまいます。このため、胎児の心電図計測はきわめて困難で、従来は超音波診断装置(エコー装置)を利用するしかありませんでしたが、このエコー検査では形態しかわかりません。一方、磁力線は胎脂の影響を受けずに通過するので、心磁図計測が可能になります。また、磁場強度は発生源からの距離に応じて急速に減衰するため、妊婦の心磁界の影響を受けることなく、胎児の心磁界のみを測定するMCG技術が将来開発される可能性もあります。
図8 将来期待されるMR磁気センサを用いた心磁計による胎児の心磁界計測(イメージ)
さらには、非侵襲で微弱な生体磁場を簡便に測定できることで、医療用としてのみならず、ウェアラブルなヘルスケア機器やスポーツ科学などの分野でも応用が期待できます。
まとめ
生体磁場の測定などに使われているSQUID磁束計は、システムそのものが高額で大がかりなうえに、冷却用の液体ヘリウムを定期的に補充する必要があるなど、ランニングコストもかさむという根本的な難点があります。このため、低コストで使い勝手にすぐれたSQUID磁束計にかわるシステムは、多くの臨床医の関心を惹くことが期待されます。
こうしたニーズに応え、TDKはHDDヘッド製造で培った先進の薄膜技術とスピントロニクス技術を利用し、小型・高感度のMR磁気センサを用いた生体磁気センサを開発中です。その磁気分解能は従来のMR磁気センサの約1000倍の数十pT(10-11T)に及び、SQUID磁束計の領域に迫っています。また、TDKは東京医科歯科大学大学院との共同研究により、多チャンネルのMR磁気センサアレイによる生体磁気測定システムのプロトタイプを開発し、2016年には常温による心磁界のPoC計測と心臓磁場分布の可視化にも世界で初めて成功しました。2019年には心臓の磁場分布のリアルタイムの測定に、2024年には通常の環境下(磁気シールドルームレス)における心磁計測に、それぞれ世界で初めて成功しました。
TDKでは現在、分解能が数pTの生体磁場測定システムの開発も進めています。これまでSQUID磁束計でしか測定できなかった領域に、さらに迫ることで、心房細動などの心房性疾患の診断にも期待できます。
また、数pTという分解能は、心磁界よりも微弱な脳磁界の計測の可能性もあるレベルです。生体磁場については、心磁図よりも脳磁図の研究のほうが活発です。電位差計測する脳波計とくらべて、脳磁計は頭蓋骨の影響を受けないことが期待されるため、シャープな情報が得られるのが特長です。ただし、てんかん患者に特有の脳波波形を発生させている異常部位の特定や、難病であるALS(筋萎縮性側索硬化症)の原因解明、瞑想状態の脳から発生するα波の解明などには、0.5pT以下の分解能が求められると考えられます。MR磁気センサにおいては至難の技術領域ですが、TDKではMR磁気センサならではの特長と持ち味を活かして、最先端の生体磁場の研究に資するべく、努力を続けてまいります。
TDKのMR磁気センサは、生体磁場測定以外にも、さまざまなアプリケーションの可能性が広がっています。常温かつ非侵襲での計測を目的に設計されているため、たとえば、目視では発見できない微細な欠陥を検査する磁気探傷試験(MT)など、非破壊検査の分野での応用も可能です。
また、MR素子ならではの小ささを活かして、体内検査デバイスや人工臓器などへの応用も考えられます。
きわめて高感度な生体磁場測定を簡便・低コストで実現する生体磁気測定システムと、先進のスピントロニクス技術によるTDKの磁気センサ技術の今後にご注目ください。
TDKはMR磁気センサをはじめとする磁気センサ技術のさまざまな応用展開に取り組んでいます。
本記事でご紹介したTDKの技術・製品により、お役立てできる案件がございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。なお、TDKではMR磁気センサを用いた生体磁気測定システムをご見学・ご体験いただくためのデモンストレーションも予定しています。
お問い合わせ、資料提供などについて
-
ニューロモーフィック技術でAIのエネルギー問題を解決
TDKの開発するスピンメモリスタを使用したニューロモルフィックデバイスでAIの消費電力削減に挑戦。 -
地磁気の1000万分の1が検知可能な高感度磁気センサ
シールドなしで手軽に超微弱な磁場を測定可能。 -
厚み50μm以下、フレキシブルで曲げにも強い基板内蔵用薄膜コンデンサ
デカップリング・コンデンサのイノベーション。LSI直下の基板内に最短距離で一括内蔵。 -
Ag積層型(Agスタック)透明導電性フィルム新開発
省エネ・創エネルギーにも貢献する機能性フィルム -
SQUID(スクイド)代替を可能にする生体磁気センサ
常温で微弱な生体磁場を高感度センシング。世界初、常温センサによる心臓の磁場分布の可視化に成功。 -
次世代の光通信/光伝送システムに向けた光部品・モジュールの開発
TDKの光通信部品・モジュール開発の背景と技術